11月30日発売 週刊朝日「定年後のお金と暮らし2012」
の一部を監修しました。
第3章(5)、(6)の遺言と相続に関する部分を監修してます。
解りやすくコンパクトに、
定年後のお金と暮らしについて読めるのでお勧めです。
比較検討事例も面白いです。

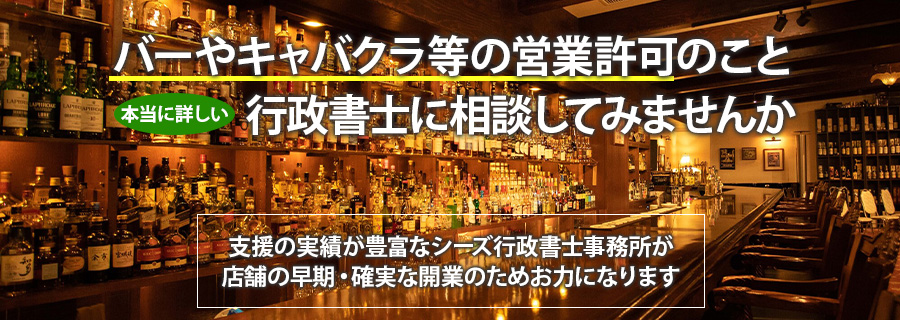
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 12月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
飲食店を始める人が増えています。
不景気といわれてきましたが、飲食店やキャバクラ(社交飲食店)の新規開業は増えています。
これは、不況で店をたたんだあと、そのまま居抜で同じ業態のお店を始める人が多いことが
影響しているようです。
居抜店舗の良いところは、基本的な設備、特に厨房回りなどがすでにそろっているので、
設備投資費用が比較的少なくて済むということ。
スケルトン工事からに比べれば、半額から1/3程度で済むこともあります。
気をつけていただきたいのは、
「前に営業許可がでていたから、大丈夫」という思い込み。
飲食店の営業許可には、一定の設備があることが問われます。居抜であっても、許可当時にはあった設備が
撤去されていることは珍しくありません。そのため、許可申請の前には必ず要件を満たしているかのチェックが
必要です。
また、キャバクラなどの社交飲食店は、新規営業許可申請をする際に、近隣に保護施設(保育園、病院、学校等)
ができていれば、新規の許可は下りません。
「前もキャバクラが営業していたので大丈夫です」と不動産事業者が勧めるままに契約してしまうと、実際は許可が
下りないトラブルに発展することがあります。
居抜物件で飲食店・社交飲食店を始める前には、必ずオーナー様自身が要件をチェックするようにしてください。
もちろん、幣所がお手伝いいたします!
発売になりました。
「親の葬儀と手続き・相続・法要のすべてがわかる本」ナツメ社
二村祐輔 中村麻美(シーズ行政書士事務所)共著
さっそく、読んで感想を下さった方がいますのでご紹介します。
『40代が読むと良いね。自分の親が死んだって、お葬式の事とか何もわからないし。
言い方とか事例がたくさんあって、これまでのハウツー本を超えた画期的な本だと思う。
考えることがたくさんあるので、著者なりの優先順位を付けてほしい』
とのこと。
大変うれしい感想です。
今わざわざお葬式の本を出すには、
「マナー本はあるけど、実際にどう話せばいいのか、誰にどんなことを聞けばいいのかが書いてある本がない」
という切実なお悩みを持つ人が多いから。
葬祭セミナーは、満員で抽選になるほど盛況です。みなさん、それほどお葬式と言うものに関心と不安をもっている
ということでしょう。
本書は、「予め考えて、心づもりをしてください。そのためには、こんなことを聞いてみましょう」と、
お坊さんにお布施の値段を聞く聞き方から、行政窓口での質問の仕方までたくさんの「言い方」「聞き方」例
を載せています。
一冊あると、きっと便利に使っていただけると思いますので、
書店でお求めください。
『親の葬儀と手続き・相続・法要のすべてがわかる本』
2月15日ごろ、ナツメ社より発売になります。
日本葬祭アカデミーの二村祐輔氏、シーズ行政書士事務所 行政書士中村麻美の共著です。
お葬式のハウツーではなく、
お葬式ってそもそもどんな意味・意義があるのかから始まり、
納得できる良いお葬式をするにはどんなことを心づもりしたらいいのか、
良い葬儀社はどうやって探せばいいのかなど、踏み込んで解説しています。
また、
相続に関しても、タイムスケジュールや必要な手続きをご案内していますので、
一冊あればいざという時きっと役立ちます。
それ以上に、お葬式に対する考え方がガラッと変わるかもしれません。
「家族葬」「直葬」などのキーワードから、お葬式に対する考え方の変化や時代背景の変化を優しく解説しています。
そして、「ではどうすればいいのか」という答えもご用意しています。
今や、お葬式も予習して備える時代です。是非お手に取ってみてください。
昨年は皆様のお力添えをいただき誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
シーズ行政書士事務所では、相続分野の専門家とネットワークを作り、
相続手続きでお悩みのお客様のご相談も承っております。
ご相談は完全予約制となっておりますので、事前にお電話でご予約ください。
弊所が窓口となって、お客様に最適なプランを作成したうえ、各専門家と提携して手続きを進めます。
「誰に頼んだらいいのか解らない」「何から始めたらいいのか解らない」とお悩みの際は、
是非ご相談ください。
詳しくは専用HPで http://seeds-souzoku.com/
引き続き、会社設立、許可・認可分野の専門家としても業務範囲を拡大しております。
本年も皆様のお力となれるよう、知識・専門性に磨きをかけ、
「頼れるパートナー」であり続けます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
東京都行政書士会主催の無料セミナーのご案内です。
なんと、たった1回のセミナーにお墓もお葬式も遺言も全部入ってます。「ライフエンディングステージ」の
心配事・解らないことが一気に解決。わかれば安心!
セミナーと並行して行政書士による無料相談も行っています。
漠然とした不安がある人は、まずはセミナーを聞いて、それから考えをまとめて相談を受けることをお勧めします。
無料相談だけもOKです。
定員に達し次第お申し込みを締め切りますので、お早めにお電話下さい。
●第1部 あなたらしいお葬式 二村 祐輔(葬祭カウンセラー)
・・・お葬式やお墓の不安解消
二村先生は、長年消費者セミナーなどでお葬式やお墓の意義、「自由なお葬式」について講演されてきました。
「お葬式はいらない」と感じている方、お葬式に意味や価値を見いだせなくなっている人に是非聞いていただきたい
お話です。
二村先生が主催する日本葬祭アカデミーのHPはこちら ⇒ http://www.jf-aa.jp/
●第2部 あなたらしい遺言の書き方 菊田 民治(行政書士:東京都行政書士会理事、市民法務部部員)
・・・あなたの願いをかなえて、遺族の争いを未然に防ぐことができる「遺言書」の書き方
●第3部 あなたらしい成年後見を考える
粂 智仁(行政書士:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター業務執行理事)
・・・どんなときでも「あなたらしく」あるための、「成年後見」を考える
★★お申込みは、お電話またはFAXにて★★
電話 東京都行政書士会事務局 :03-3477-2881
FAX:03-3463-0669 (*「市民フォーラム参加希望」として、お名前、ご連絡先電話番号をお送りください。)
締め切り12月13日(火) *定員になり次第締め切らせていただきます
参加無料
日時 12月20日(火)
受付開始:午後 1時30分 14時開演 16:45終了
相続、遺言、成年後見に関する相談会併設
場所 文京シビックホール小ホール
11月30日に週刊朝日「定年後のお金と暮らし2012」が発売になりました。
このところ毎年出ているおなじみのシリーズです。
今回は、大幅にリニューアルするということで、
弊所がお手伝いして今まで載せていた遺言や相続の記事も新しくすることに。
初体験の雑誌記事取材から完成までをお伝えします。
まず、ライターさんが事務所に来てくれて、「公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言」それぞれの違いや、
メリット、デメリットについて取材がありました。
普段あまり意識しないのですが、遺言を話すときにはどうしても法律用語が多くなります。
それらの言葉自体難しく、「公正証書遺言は公証人が相談に乗ってくれて・・・」といったところで、
「相談」になるまでに自力で考えなどをまとめるのが難しい、ということが図らずとも伝わったようです。
弊所としましても、公証人と話しながら遺言を作るのは、一般的にはかなりハードルが高いと考え、
遺言者と公証人の間に入って「通訳」しながら公正証書遺言を作っていくサービスを提供しています。
そして、校正といって事実関係の間違いや誤字・脱字などのチェックがあります。
今回、相続関係説明図を入れてもらったのですが、
なかなかイメージが伝わらず苦労されていました。
何度か修正が入ったかいあって、出来上がりはばっちりです!
弊所では、「子供のいない夫婦はお互いに遺言書を作りましょう」と勧めていますが、
上記の関係図を見ていただければ、「なるほど!」と思っていただけるはず。
この雑誌は2~3カ月程度継続して書店に置かれるそうなので、見かけたらぜひ手にとって見てください。
比較検討事例が豊富で、「へ~」というネタがたくさんあります。
先週、葬祭企業様向けに個人情報保護のセミナーを行いました。
このセミナーは、「P・I・P認証認定」企業様向けの、更新講習です。
P・I・Pは、「パーソナル インフォメーション プロテクト」の意味で、一般社団法人日本葬祭情報管理協議会が
葬祭企業様向けの認定講習会を行っています。
お葬式というのは、葬儀社だけでなく、仕出し料理店 (通夜振る舞いや精進落とし)、生花店(花輪、供花)、
ハイヤーやマイクロバスの会社(火葬場への移動)、贈答品店(返礼品や香典返し)など、多数の企業が関わります。
もし、喪主がいちいち企業ごとに契約・発注を行わなければいけないとしたら、それは大変な苦労です。
そこで、葬儀社が喪主に代わって各協力企業に対して、葬儀の情報提供を行っています。
その「情報」は、葬家(お葬式を行う家)や喪主の名前から始まり、故人が生前に勤めていた会社など、
大変センシティブな情報です。
この情報を扱うには、細心の注意が必要なのですが、残念ながら葬祭業界に置いて、「個人情報を保護する」
という意識は高くありません。「緊急事態だからしかたない」と、むしろ、なおざりにされています。
「お葬式の値段」「喪主の住所、家族構成」「仕出し料理の値段と発注数」などが書かれた用紙が、
不用意にFAXされたりしています。
情報提供・共有自体は、予め喪主に使用方法や提供範囲を説明すれば問題ないのですが、
「面倒だから」と、全ての情報を全ての範囲に送ってしまうのは問題です。
こうした問題に鑑み、個人情報の取り扱いを真剣に考える葬儀社を増やしたい、という活動を上記社団法人は
行っています。
最近では、PC上からの情報流出という、新しい問題も起こりつつありますので、
「PC上で顧客情報を管理するときのルール、情報漏えいへの防御策」についても、私がお話しさせていただきました。
こうした活動を通じて、「お客様に選ばれる地域の葬儀社」としての地位を確立していただきたいと思います。
そして、「個人情報」に対してアレルギー反応のような過剰反応をする人もいますが、
正しく取得して、正しく使用し、正しく管理する ことができていれば、
恐れることはないということを解っていただきたいと思っています。
一般社団法人日本葬祭情報管理協議会のHPはこちら http://www.jfima.jp/
個人情報保護とこれからの葬祭ビジネス
について講義する
二村祐輔氏(日本葬祭アカデミー代表)
会社を作るときは、作る前に考えるべきことが色々あります。
例えば、資本金の金額によっては初年度から消費税の課税事業者になるとか、出資割合は?お給料はいくらくらい
がいい?とか。
設立後に許可や認可を取る予定ならば、定款作成時に所定の目的を必ず入れなければいけないとか、
そんなことが沢山あります。
ポイントが解っていれば、本やネットで探して調べればいいのですが、実際自分の事業に即してどんなことに
気をつければいいのかを調べるのは至難の業です。
そこで、お勧めしたいのが、特に税金や節税、事業承継に関しては信頼できる税理士に相談すること、です。
「信頼できる税理士ってどうやって探すの?」という人は、
東京上板橋の「久保税務会計事務所」に一度相談してみてください。この道32年のベテラン所長が相談に乗ってくれます。
なんと、無料。
所長は「会社を作る前にぜひ相談してほしい。融資のこと、節税のこと、事業承継のこと等について社長さんにとってベストなものを、
今までの経験からお話しさせてもらいます。顧問契約をしなければいけないなど考えずに、無料相談だけでも来てください。
きっとお役に立つと思います。」と話していました。
会社を作って成長発展・継続させ、そして、その会社を次代へ承継するところまで相談できるので、
とても頼りなりますし、きっと長いお付き合いができるでしょう。
そして、所長のお話はとても面白いです!一度お話ししただけですが、すっかりファンになってしまいました。
「ああ、これは弊所のお客様を連れて行って差し上げたい。具体的な相談をしてみたい」と思ったほど。
いいものは、みんなに紹介したい!
ということで、所長の許可を得て紹介させていただきました。
さあ、さっそく相談してみてくださいね。久保税務会計事務所のHPはこちらです↓
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 12月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||