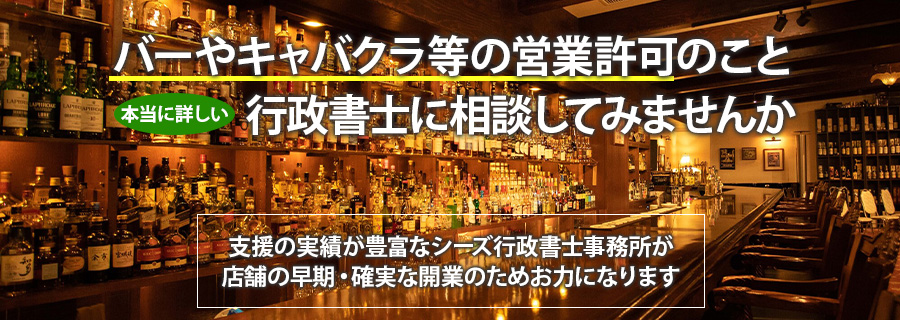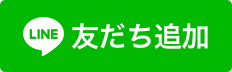判例タイムズです。
話題の判例とかが載ってるアレですね。私が読んでいるのは家庭裁判所制度40周年記念 臨時増刊号です。
「遺産分割・遺言215題」とタイトルが付いています。
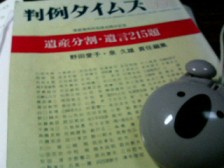 (判例タイム第688号 1989年4月10日号)
(判例タイム第688号 1989年4月10日号)
最近遺言書がはやっています。
遺言書キットなんかも販売されてますよね。「遺言書かきたい」と言う人も、
「遺言書書いた方がいいよ」と言う人も、ともに増えてきているようです。この仕事始めるまでは、
意識したこともなかったですけど、夕方のTVニュースでも相続トラブルについて取り上げられることが
多くなったような気がします。
で、色々相談もあり、こちらから仕掛けていく営業もあり、で、判例タイムスを読んで「へ~」と勉強しているわけです。
遺言書は、不備や紛らわしい記載があっても「これ、どうなんですか?」って本人に確認できません(亡くなっているので)
だから、記載要件がとても厳しいです。
「それくらいおまけしてよ!普通の人の感覚だったらわかるでしょ!」ということも、真剣に裁判で争われてしまうのです。
日付。遺言書には日付を書きます。「吉日」って書いたら無効というのは有名な話ですね。これ、本当に無効になりますので、
要注意です。
では、遺言書本体には日付がなく、封筒に日付が書いてあったら?
これも、「遺言書に押した印鑑で封筒に封印してあるなど、一体であることが分かれば有効である」そうです。
うっかりした人だと、遺言書を実際に書いた日付と、記載した日付が違ったりするかもしれないですね。そんな時はどうするのでしょうか・・・。
答え:錯誤によるものと証明できれば、有効な遺言書になる(かなり簡略化して判旨を書いてますので、受験生の皆さんはこのまま
覚えないように!)
なんてことが、最高裁まで争われているのですね~。
遺言書の体裁に関する相談ももちろんありますが、「私のお葬式はこうして欲しいの!」と遺言書に書きたいという
相談も結構あります。書いてもいいです、しかし、効力の話以前に、
遺言書に書いても、きっとお葬式が終わってから、遺族は遺言書を発見するのでしょうね・・・・。
色々なご希望がありますので、遺言書と言うことにこだわらず、お客様のご希望をかなえるご提案をさせていただいております。